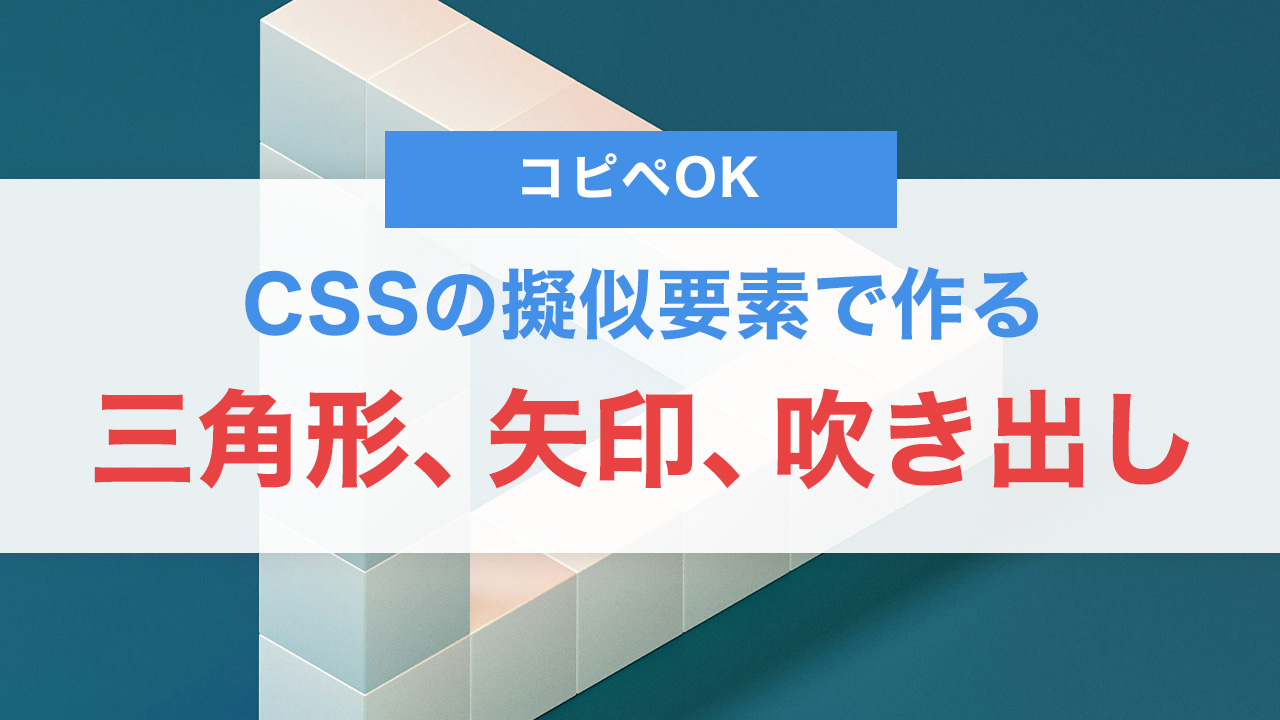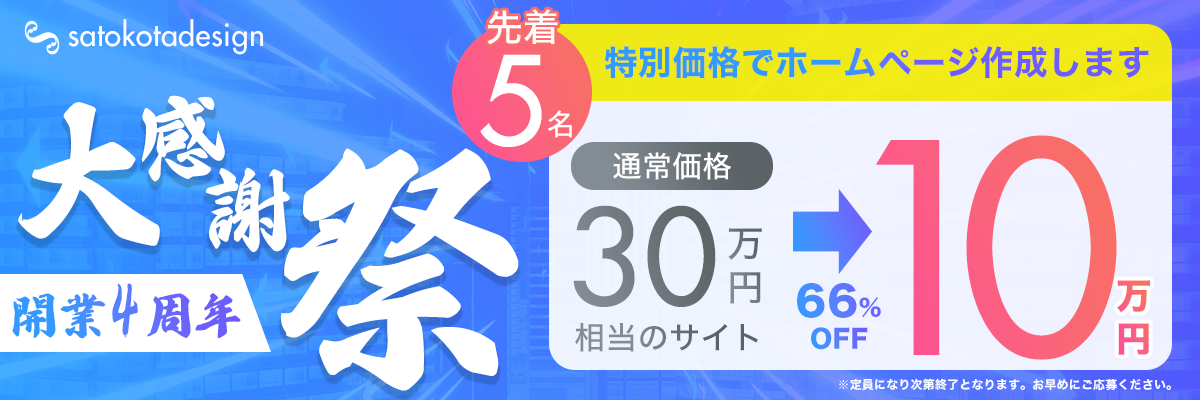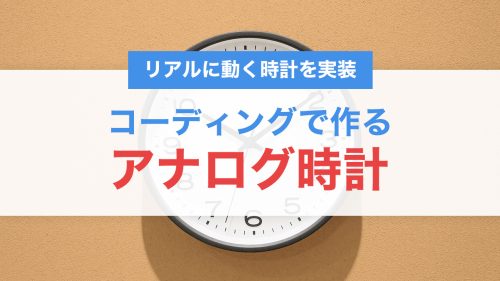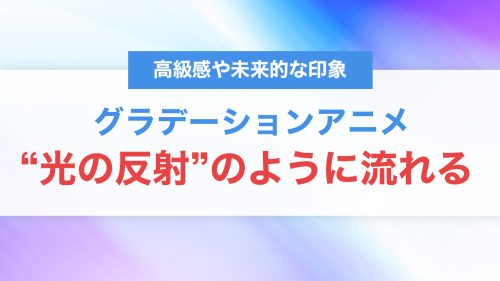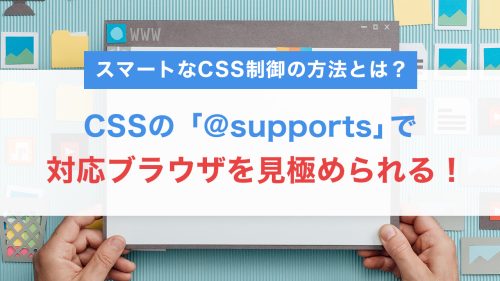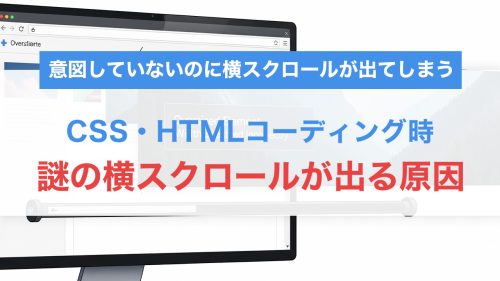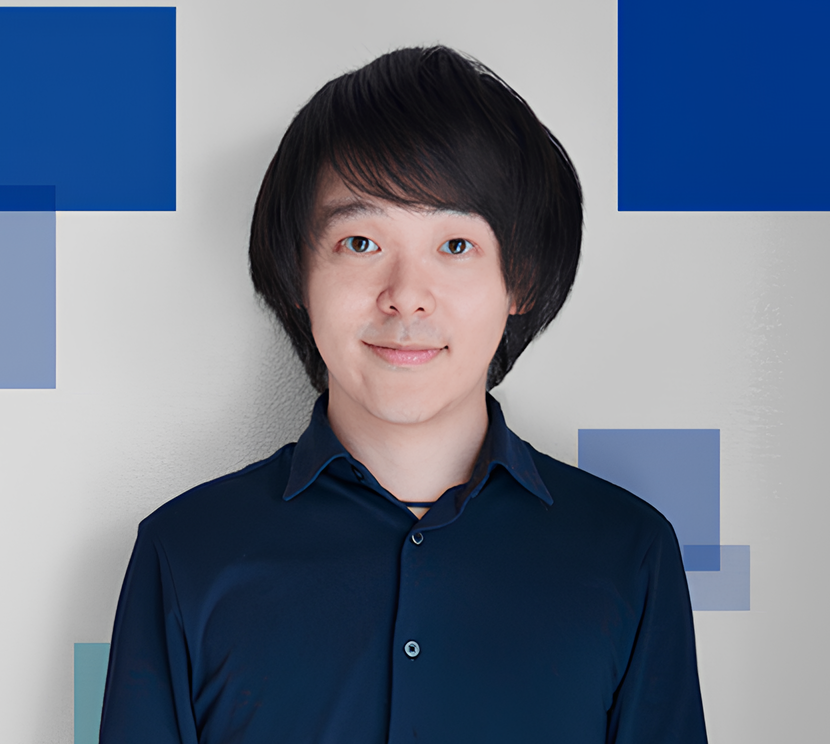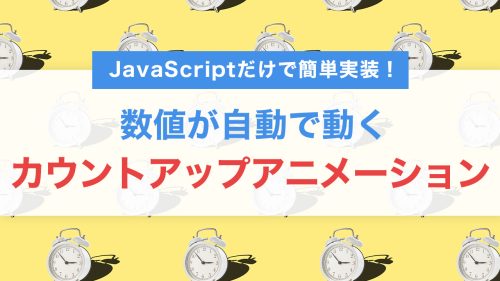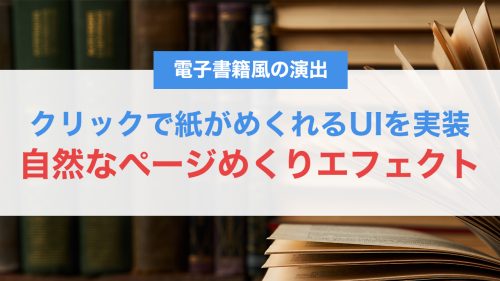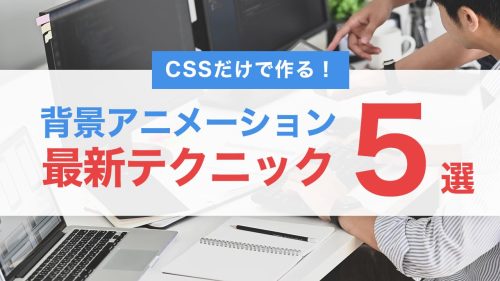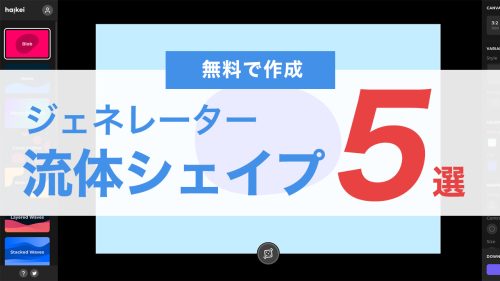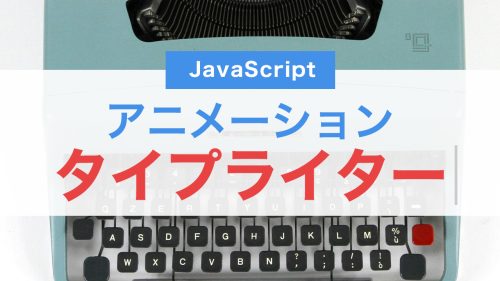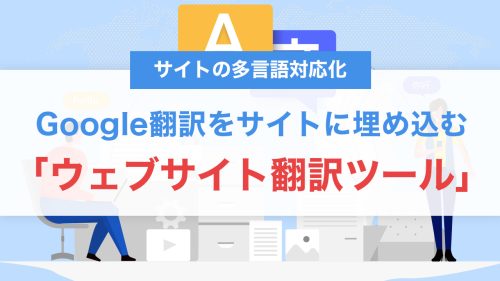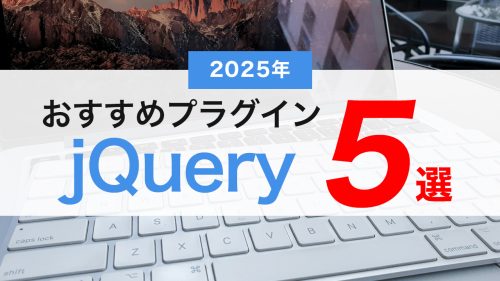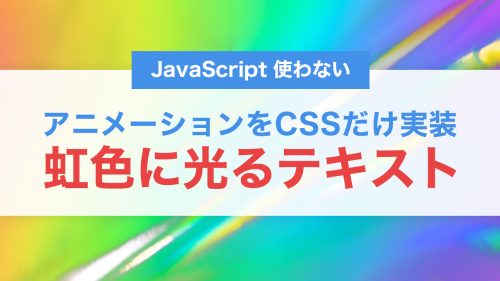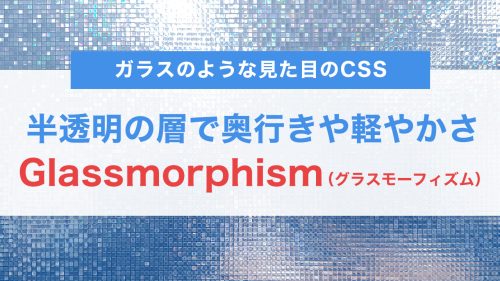こんにちは!静岡県浜松市でWEBデザイナーをしています小瀧です。
今回はCSSだけで実装できる「立体ボタン風エフェクト」をご紹介します。
JavaScriptを使わなくても、ちょっとした工夫で“押したくなるボタン”を作れるんですよ。
特に最近は、シンプルだけど印象に残るUIが好まれる傾向にあるので、CSSだけで実装できるこうしたテクニックはとても重宝します。
この記事では、「ホバー時に立体的に見えるボタンエフェクト」の基本から応用まで、しっかり解説していきます。
そもそも“立体感のあるボタン”って?
Webデザインにおける立体ボタンとは、「押せそうに見えるボタン」のことです!
フラットデザインが主流になった今でも、「ユーザーがすぐに操作対象とわかる」ボタンUIはとても重要です。
実際に効果的なボタンとは
- 影がついていて浮き上がって見える
- ホバー時に凹んだように変化する
- 操作時に視覚的なリアクションがある
こういった効果をJavaScriptを使わず、CSSだけで実現する方法をご紹介していきます。
基本のスタイル:立体ボタンの作り方
まずは基本となる立体ボタンのCSSスタイルです。
ここでは「box-shadow」を活用して、ホバー時の凹みエフェクトも加えて浮き上がるような効果を与えています。
See the Pen
Untitled by 小瀧賢 (@ekwwawpb-the-styleful)
on CodePen.
これだけで、立体的に浮き上がって見える+ホバーで凹むという自然なアニメーションができます。
応用編:アニメーションを追加してもっとリッチに
CSSのtransitionプロパティを使って、よりスムーズなアニメーションを実装しましょう。
またactive状態も加えると、クリック時に押し込まれるような動きが出せます。
See the Pen
Untitled by 小瀧賢 (@ekwwawpb-the-styleful)
on CodePen.
ちょっとした違いですが、ユーザー体験にはとても大きな影響を与えます。
「押した感」があるだけで、信頼感・操作感がグッと高まるんですよね。
デザインのバリエーションアイデア
立体ボタンはアイデア次第で多彩にアレンジできます。
- グラデーション+影 背景にリニアグラデーションを入れて、よりリアルな光の印象を追加。
- 押した後に色を変える :activeで色を変えて「押された感」を視覚で表現。
- アイコン入りのボタン FontAwesomeなどのアイコンと組み合わせてより視覚的に。
ボタンデザインのチェックポイント
実際に使う際には以下のポイントにも注意しましょう。
- 背景とコントラストを保つこと(アクセシビリティ)
- タップ領域は十分に確保(特にスマホ)
- クリックしても「何が起きるか」が明確(ラベルやアイコンの活用)
こうした配慮をすることで、ボタンの“見た目以上”の価値をユーザーに届けられます。
まとめ
ボタンはただのクリック用の部品ではありません。
ユーザーに安心して操作してもらうための「きっかけ」であり、デザインの中でも重要な要素です。
今回ご紹介した立体ボタン風のCSSエフェクトは、実装がシンプルで汎用性が高いのも魅力です。
ぜひ、ご自身のWeb制作に取り入れてみてくださいね。
次回もCSSだけでできる面白いUI表現を紹介していきますので、お楽しみに!