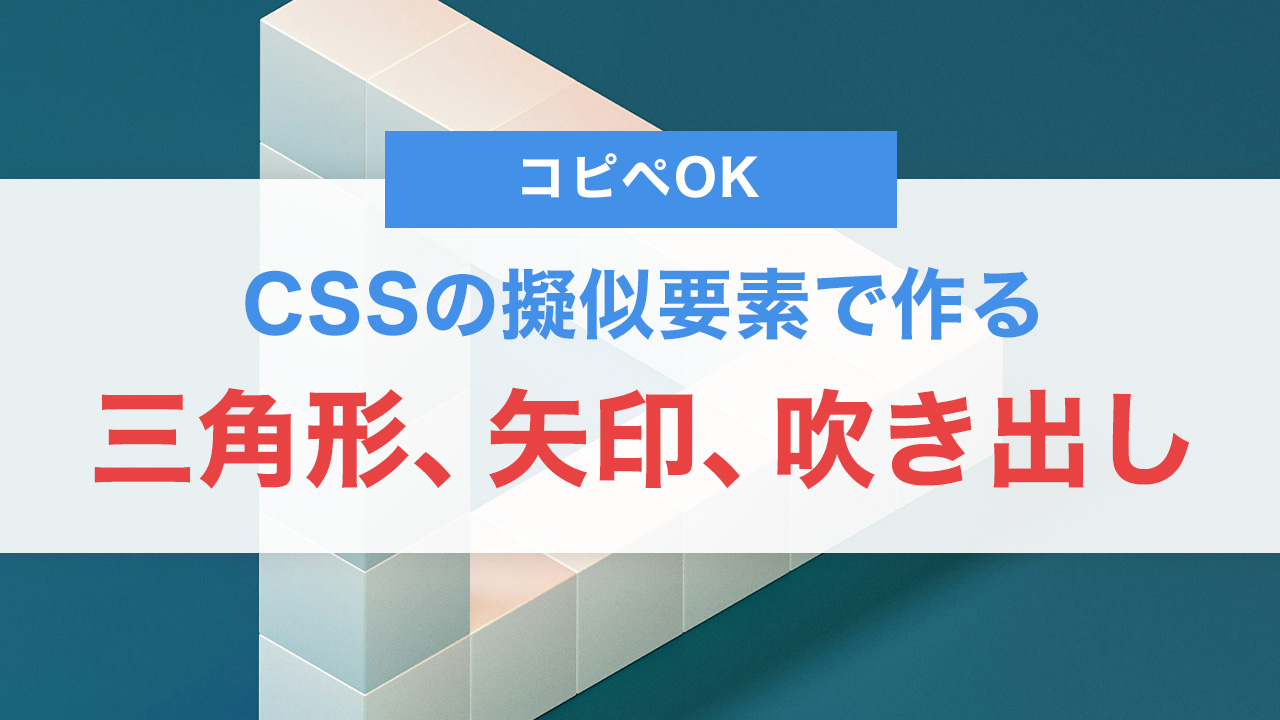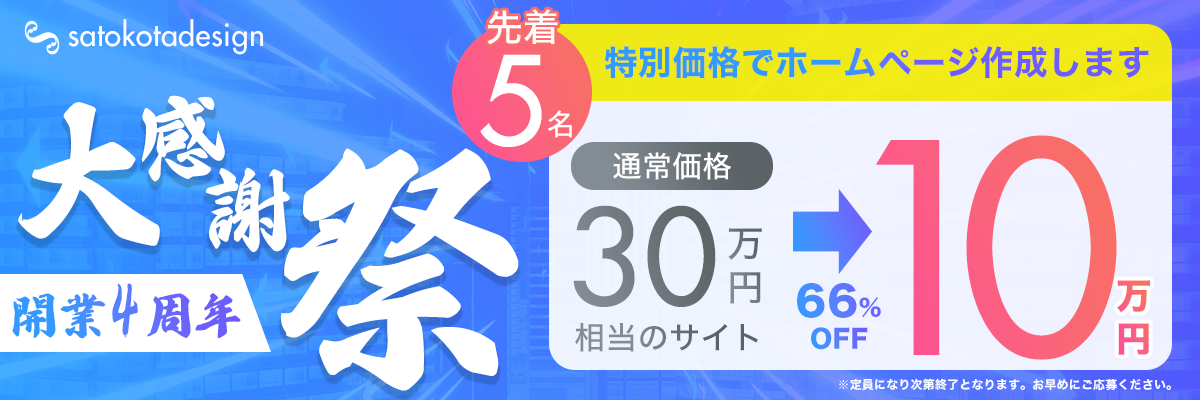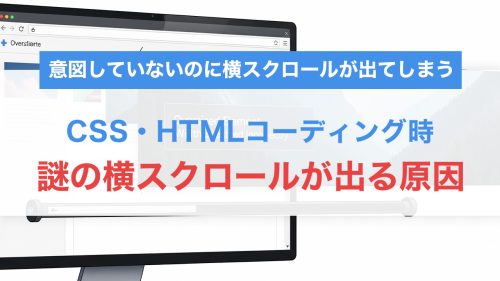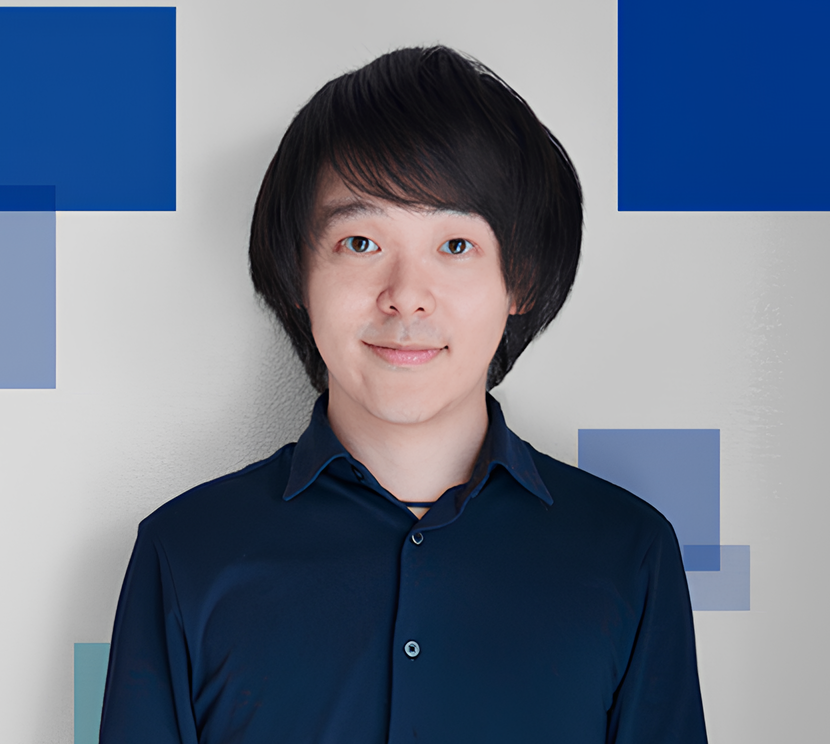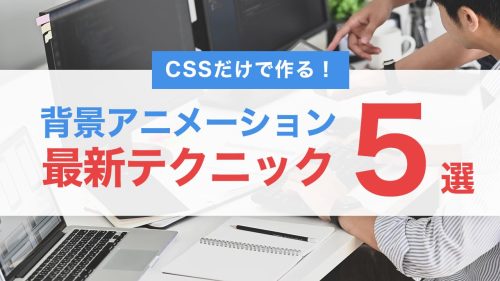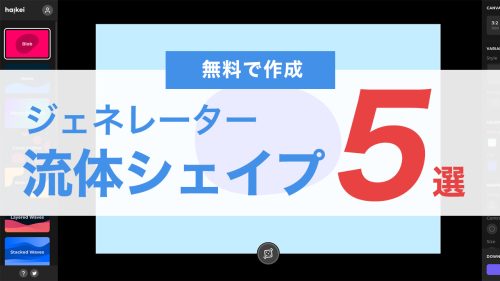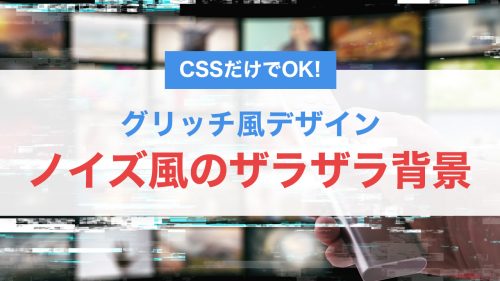こんにちは!静岡県浜松市でWEBデザイナーをしています小瀧です。
Web制作の現場で「コーディングの気づかい」という言葉を耳にしたことはありますか?
デザインカンプを忠実に再現することはもちろん大切ですが、制作ディレクターの視点から見ると、それ以上に“細やかな配慮”ができるコーダーかどうかが評価の分かれ目になります。
例えば
- レスポンシブでの崩れを事前に想定して対応しているか
- 将来の運用・更新を見越してCSS設計がされているか
- アクセシビリティやパフォーマンスへの配慮が自然に盛り込まれているか
こうした「気づかい」は、クライアントやユーザーの信頼だけでなく、制作チーム全体の効率と完成度を大きく左右する目に見えない品質です。
今回は、制作ディレクターの立場から見た「コーディングの気づかい」の具体例を掘り下げ、現場で重宝されるコーダーになるためのポイントをお伝えします。
制作ディレクターが評価する“気づかい”とは
1. デザイン再現度+αの提案力

デザインをそのままコーディングするだけでなく、デザイナーの意図を汲み取り、より良い体験にする提案が求められます。
- 文字詰めや余白の微調整で可読性を向上
- アニメーションを付加して操作感を向上
- hoverやfocus時の挙動を自然に整える
単なる「指示通り」ではなく、ユーザー目線での最適化が評価されます。
2. 更新・運用を想定したコード設計

納品後も更新が続くWebサイトでは、メンテナンス性の高いコードが重要です。
- クラス名は意味のある命名規則(BEMなど)を用いる
- 冗長なスタイルを避け、共通化・変数化する
- コメントを適切に残しておく
これらは後任のエンジニアや運用担当者にとって大きな助けになります。
3. パフォーマンス・アクセシビリティへの配慮

制作ディレクターが嬉しいのは、目に見えにくい部分まで気を配るコーダーです。
- 画像の適切な圧縮とWebP/AVIF対応
- 不要なライブラリを削除して軽量化
- alt属性やラベル付けでスクリーンリーダー対応
これらの改善はUXだけでなくSEO評価にも直結します。
実際の現場での「気づかい」事例
ケース1:想定外の解像度で崩れを防ぐ
ディレクターから「スマホ対応は375px前提で」と指示があった場合でも、
横幅320pxや横向き表示で崩れないかを自発的に確認するコーダーは信頼されます。
ケース2:納期前の微調整を提案
公開直前の段階で、「このボタンの余白をもう少し広げた方がタップしやすい」といった改善提案を行えるコーダーは、ディレクターにとって頼れる右腕の存在です。
気づかいを身につけるための習慣
- 常にユーザー目線でサイトを触る
- チーム内レビューや他人のコードから学ぶ
- 新しいCSS/JS仕様やアクセシビリティ基準を追いかける
気づかいは一朝一夕で身につくものではありませんが、日常的なチェックと改善の積み重ねが重要です。
まとめ
コーディングの気づかい3要素
・デザイン再現+ユーザー目線の最適化
・メンテナンス性を考えた設計
・パフォーマンス・アクセシビリティへの配慮
・メンテナンス性を考えた設計
・パフォーマンス・アクセシビリティへの配慮